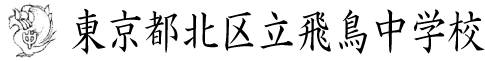3学年理科 南中高度の測定(夏と冬)で太陽高度を観察中
- 公開日
- 2016/11/28
- 更新日
- 2016/11/28
学習・学力向上
3学年理科 南中高度の測定(夏と冬)で太陽高度を観察中
●南中高度というのは、太陽が真南にきて、いちばん高く上がったときの地平線との間の角度です。 太陽の南中高度は場所によって違います。 夏至のとき(南中高度がいちばん高くなります)と冬至のとき(南中高度がいちばん低くなります)の太陽の南中高度は、その場所の緯度がわかれば簡単に計算することができます。
●建物の影の状態を計算するなどのために、太陽の南中高度を知りたいことがあります。南中高度というのは、太陽が真南にきて、いちばん高く上がったときの地平線との間の角度です。太陽の南中高度は場所によって違います。夏至のとき(南中高度がいちばん高くなります)と冬至のとき(南中高度がいちばん低くなります)の太陽の南中高度は、その場所の緯度がわかれば簡単に計算することができます。
•夏至のときの太陽の南中高度(度) = 90 − (その場所の緯度) + 23.4
•冬至のときの太陽の南中高度(度) = 90 − (その場所の緯度) − 23.4
それ以外のときには、太陽が北寄りに位置しているのか、南寄りに位置しているのかを示す「視赤緯」の値が、計算に必要となり、以下の式で計算することができます。
•太陽の南中高度(度) = 90 − (その場所の緯度) + (太陽の視赤緯)
毎日の太陽の視赤緯の値は、国立天文台が編纂する「理科年表」などに載っています。