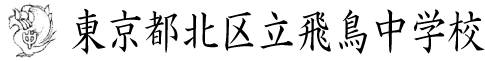2月24日(月)都立高校一般入試無事に終了!合格発表日は2月28日(金)
- 公開日
- 2014/02/25
- 更新日
- 2014/02/25
学習・学力向上
2月24日(月)都立高校一般入試無事に終了!合格発表日は2月28日(金)
15歳の春に花咲くことを祈ります。頑張りました!
<東京新聞WeB版より> ※高校入試の様子写真も東京新聞より
東京都立高校入試は二十四日に実施、合格発表は二十八日。願書取り下げや再提出の結果、定員割れは、七日の願書締め切り時点の二十九校から十四校に減った。
都立高の入試日は〇五年度以降、二月二十三日とされてきたが、今回は東京マラソンと重なったため、入試を一日遅らせた。倍率は前年度よりやや低いが、〇九年度以降、一・五倍台の高倍率が続いている。
都教育委員会は十四日、二〇一四年度都立高校入試の最終応募状況をまとめた。全日制全体の最終応募倍率は前年度より〇・〇一ポイント低い一・五〇倍だった。
百七十三校で三万千八百一人の募集人員に対し、最終的に四万七千八百五十人が応募した。普通科男子は日比谷が九年連続トップの二・九九倍、女子は広尾の二・七一倍が最も高かった。男女合わせた倍率も最高は広尾の二・六七倍。専門学科は国際の三・六〇倍だった。
以下、入試問題の主な解説。詳細は各社新聞記事等を参照ください。
【国語】
大問五題、小問二十五題の問題構成は例年通りである。
大問1、2はいずれも基本的な漢字の問題だ。ただし、日常ではあまり使用しない「銘菓」や書き誤りやすい「陸橋」については語彙(ごい)力も問われることになる。
大問3は紺野先生と少年との交流を描いた小説からの出題。表現の特徴や人物の心情、様子などを問う問題が中心である。問5は「話す言葉」を書く問題。文章に即して心情をとらえるだけでなく、適切な言葉で簡潔に表現する力も要求される。
大問4の説明的な文章は環境問題について書かれた文章である。難解な語彙もあるが、論旨が分かりやすく内容は理解しやすい。設問は論理構成や内容理解を問う基本的な問題が中心である。問5はテーマに関して具体的な体験や見聞を示して意見を発表するもので、自分の考えを論理的に表現する力が問われている。
大問5は「百人一首」に関する対談の記録や文章など、複数の資料からの出題。古典ならびに現代の文章の内容をとらえる問題や発言の役割を問う問題、指定語句による短作文の問題などがあり、総合的な問題となっている。
全体としては言語能力を幅広く問う問題になっており、日常的な学習へのしっかりした取り組みが求められる。 (目黒区立第七中学校 人見誠主幹教諭)
【数学】
問題の構成は大問が五問、小問が十九問で、これは例年通りである。
大問1は、各領域に関する基礎的、基本的な事項についての知識、理解および数学的な技能を問うものである。正負の数の計算、文字式、平方根、一次方程式、連立方程式、二次方程式、資料の活用、円周角と中心角の関係を使って角度を求める、垂線の作図を使って回転移動した図形をかく、という順番に計九問出題された。
大問2は、昨年度と同じように数学的な活動の場面を基に、数の規則性について考える問題である。問1は場合の数、問2は文字式の利用に関する証明問題である。数学的な見方や考え方に基づいて数理的に考察し処理、表現する力が必要とされる。
大問3は、関数の問題である。問1はy=ax^2の変域に関する基礎的な問題、問2(1)は二点を通る直線の式を求める問題、(2)は座標平面上の図形の面積から、点の座標を求める問題である。
大問4は、平面図形に関する問題である。問1は文字を使って角度を表す問題、問2(1)は平行線の性質を使い三角形の相似を証明する問題、(2)は相似比などを使って三角形の面積について考える問題である。
大問5は、空間図形に関する問題である。問1は二直線の位置関係を考える問題、問2は平面と直線の垂直な関係に着目し、与えられた条件から三角すいの体積を求める問題である。 (世田谷区立烏山中学校 塚本桂子主幹教諭)
【英語】
英語を理解する能力を中心として、中学校三年間で身に付けるべき英語力をみることができる問題構成となっている。
大問1は、三つの日常会話とラジオ放送のイベント情報を聞いて必要な部分を聞き取る問題である。二回の繰り返しで具体的な内容や大切な情報を聞き取る力が求められる。
大問2は、地図やパンフレットと会話文、スピーチ文が関連する問題である。ここでは複数の情報を統合させて課題を解決する力が求められている。英作文では「これから学びたいこと」という自分の考えを三文の英文で書くので、和文英訳ではない英作文力が身に付いている必要がある。
大問3は四百語程度の対話文、大問4は六百語程度の物語文である。両問ともに、まず話の流れや概要をつかんだ上で、設問で問われている情報を具体的に読み取ることが大切である。相当量の英文を一定時間で読み取らねばならないので、和訳に頼らずに一分間で百語程度の英文が読み取れる読解力が求められる。
全体として、概要や必要な情報をつかむ、話し手や書き手の意向を理解する、自分の考えを表現するという「知識を実際に活用できる英語力」が、授業中の練習や活動でどれだけ身に付いているかが問われる問題である。 (国分寺市立第一中学校 相沢秀和主任教諭)
【社会】
大問六題、小問二十題の問題構成は例年通り。昨年度一問ずつ増えた論述問題と語句記述は、本年度もその問題数のまま継承され、記述重視の傾向である。
大問1は三分野の基礎事項を問う問題。略地図中への矢印図示など、解答方法に工夫が見られる。
大問2は世界地理。地図や統計等の資料を活用し考察する能力を問う問題。今年も雨温図が出題された。
大問3は日本地理。さまざまな資料を活用して考察する問題で、やや難しい。
大問4は歴史。年表等の資料を活用して考察する問題。今年も時代順の並べ替えが二問出題された。時代の特色を掴み、歴史の流れを捉える学習が望まれる。
大問5は公民。財政や社会保障など時事的問題を取り上げ、考えさせる良問。
大問6は融合問題。世界遺産をテーマに、地形図の読み取りから、環境保全の歴史、世界遺産登録の課題まで幅広く出題された。
全体を通して、学習指導要領の趣旨を踏まえ、各種資料の活用や考察を重視する作問であった。地図や統計、年表など多様な資料を短時間で正確に分析し読み解く力や、適切に表現する力が求められている。社会科の授業では言語活動の充実や、思考、判断、表現力の育成を目指した展開がますます大切になるだろう。 (板橋区立高島第二中学校 山岡裕基子主任教諭)
【理科】
物理、化学、生物、地学の四領域からバランスよく出題され、大問六題小問二十二問の構成や領域の配列は例年通り。
大問1は、頻出のオームの法則を使った計算等、各領域の基礎的・基本的な事項を問う問題。大問2は、防災についてのレポートを読んで答える問題で、新学習指導要領で必修となった自然の恵みと災害の単元に関連している。地震波の伝わる速さ等に関する基礎的な問題であるが、レポートから有意な情報を正確に読み取る力が求められる。
大問3は、透明半球を用いた太陽や月の日周運動の観察。結果を分析・解釈する力が問われる。特に問3では地球、月、太陽の位置関係を、複数の観察の結果を関連付けて思考する。
大問4は、花のつくりと遺伝を組み合わせた出題。双眼実体顕微鏡での観察に慣れていないと戸惑うかもしれない。ここでも複数の観察の結果を関連付けて思考することが求められている。大問5は、酸と金属の反応を水素イオンに着目させて問う問題。イオンや電子の振る舞い、イオン化傾向にも踏み込んだ出題である。
大問6は、電流による磁界と電磁誘導にエネルギーの変換を組み込んで工夫された設問。相関する現象を正しく関連付けて考察する必要がある。計画的に観察・実験を行い、言語活動を充実させ、論理的な思考を深める学習が大切である。(練馬区立豊玉第二中学校 北村比左嘉主幹教諭)