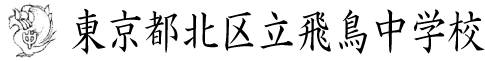本日、放送による全校朝礼を行いました。
写真は、上から順に全校朝礼時の1年生・2年生・3年生の教室の様子です。
朝礼では、私から以下の内容を伝えました。
おはようございます。校長の高田です。
3年生にとっては最後の、1・2年生にとっては、初めての学芸発表会が、今までにない形で終わりました。
合唱発表会の取り組みを通して、つらい時やうまくいかない時には頼れる仲間がいること。うまくできた時や楽しい時には、一緒に笑い喜び合える仲間がいること。そんなことが実感できたのではないでしょうか。
続きは、『 校長講話・ここをクリック 』に掲載いたしました。
校長:高田勝喜
さて、運動会や学芸発表会では『伝統を受け継ぎ』とか『飛鳥中学校の伝統を』という言葉がよく聞かれます。
では、【 伝統 】 とは、一体何でしょうか。改めて考えてみてください。
一般的には、ある集団の中で、長い間、受け継がれている考え方や習慣、技術、しきたりなどのことを【 伝統 】 といいます。
飛鳥中にも、行事や生徒会活動・部活動などさまざまな場面で、この『 伝統 』があると思います。
ただし、私は今ここで、飛鳥中の【 伝統 】 が何であるのかを話すつもりはありません。「『 伝統を受け継ぐ 』とは、どういうことか 」を、皆さんとともに確認しておきたいのです。
【 伝統 】と言う言葉には、そうすることに価値があるから受け継ぐという積極的な意味があります。単に今までがそうだったから … という、きわめて消極的な理由で受け継ぐ姿勢とは意味が違います。どういう姿勢でそれを受け継ぐのかということが重要です。
「前例踏襲」「例年どおり」といった、何となく続いているからという理由でものごとを無条件で引き継ぐことと、「 伝統を受け継ぐ 」 こととは違うのです。
真に価値があり、受け継ぐべきものだけを残し、そして、引き継いではいけないもの、つまり「 悪しき伝統 」を切り捨てていくことも、実は「 伝統を受け継ぐ 」うえで大切なことなのです。 そういった意味で、「 伝統を受け継ぐ 」ためには、変化や変革も必要であるということです。
『 伝統とは革新(改革)の連続である 』と言う言葉もあります。
変化を恐れ、現状に満足した瞬間、人も学校も進歩が止まってしまいます。常に「 より良いものを 」「 より高い位置へ 」という向上心なくして、人も組織も発展することはできません。
前例のない新しい形での『学芸発表会』を終えた今、「 伝統を受け継ぐ 」ということを改めて考えてみてください。
以上で、私の話を終わります。