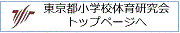研究(器械運動系)
今年度の研究
器械運動系部会 研究主題
互いに学び合い、自らの学びを深めていく体育学習
研究主題を受けた器械運動系領域部会の考え方
自分の動きを自分で見ることができなかったり、友達とアドバイスし合うことが学習課題の解決に有効であったりする器械運動の特性から、子供が自己にとって最適な学習課題を見いだしたり解決したりするには、友達と協働しながら学習に取り組むことが必要不可欠である。自分の動きに意識が向きがちな学習だが、共に運動したりグループ学習を行ったりしていく中で、共に学び合う必要感をもたさせていく。また、友達と学び合ったことで、自己も友達も学習課題が解決できたり、技能が向上できたりするような成功体験を積んでいければ、さらに協働的な学習が促され、自らの学びを深めていくことができると考える。
目指す児童像
友達と学び合うよさを実感し、学習活動を改善しながら共にできる喜びを味わえる子。
研究仮説
子供が互いに学び合う必要感をもてるようなグループ編成や学習の仕方を工夫すれば、子供たちは友達と学び合うよさを実感し、学習活動を改善しながら共にできる喜びを味わえるだろう。
今年度の研究の重点
子供が必要感を感じ、成功体験を味わえるグループ学習
研究の経過
-
9/19に品川区立後地小学校で部会を開きました。実証授業まで残すところ1月となりました。今回は部会資料を中心に検討しました。担当常任理事の木村先生よりご指導をいただき、東京都の先生方の鉄棒運動の指針と...
2025/09/24
器械運動系
-
品川区立後地小学校にて、第8回部会が開催されました。実証授業まで残すところ、あと1ヶ月と1週間となりました。夏季合同研究会で協議していただいたことを元に、資料を再考して持ち寄りました。新たに2人の先生...
2025/09/09
器械運動系
-
8月20日に夏季合同研究会が行われました。器械運動系領域部会の分科会には、総勢134名の先生方が参加してくださいました。協議会では多くのご意見をいただきました。今後、さらに部会で検討を重ね、実証授業で...
2025/09/02
器械運動系
-
品川区立後地小学校にて部会を開きました。今日は担当指導主事の黒澤先生が部会に参加してくださいました。研究の土台である「自ら学び続ける力」と「学習課題の定義」についてたっぷりと議論を重ねました。鉄棒運動...
2025/07/11
器械運動系
-
6月27日(金)東久留米市立第二小学校にて実技研修会を開きました。器械運動系領域部会の部員以外にも多くの方に参加していただき、48名にのぼりました。感覚つくりの運動の気をつける点や、下り技を中心とした...
2025/06/30
器械運動系
-
◯実証授業を終えて(成果と課題)ー第7時で技に対する言葉がけを多く行なったところ、運動とのかかわりの「する」が高かった。もっと前の時間から技についての言葉がけを多く行なっても良かった。例えば2、3時間...
2024/12/11
器械運動系
-
実証授業に向けて学習過程〇2時間目、3時間目の後半でそれぞれ前転・後転、倒立・倒立回転の技の指導をするのか。または、2、3時間目に中核となる技術に取り組み、4、5時間目に技の指導をするのか。技と出会わ...
2024/09/10
器械運動系
-
令和6年8月9日金曜日、品川区立後地小学校にて第8回器械運動領域部会を行いました。 ◯常任理事の先生から 永瀬校長先生 夏休み、間もなく前半の折り返し。資料、よくまとまっています。夏季合研も充実した...
2024/08/20
器械運動系
-
令和6年8月1日木曜日、品川区立後地小学校にて第7回器械運動領域部会を行いました。 【常任理事の先生から】 須藤校長先生 先週、全国体育実技指導者講習会が行われました。全国から多くの先生方が集まっ...
2024/08/07
器械運動系
-
◯主題の捉え 「多様なできた」に運動遊びを入れていいのか。「技ができた」「練習の場でできた」など3年生の機械運動の目標を目指した方がいい。 「できそう」→「できた」なのか。「できた」→「できそう」...
2024/07/22
器械運動系
令和5年度の手立て
1.共に行う感覚つくりの運動や練習方法の開発
2.グループ編成・グループ学習の仕方
会場校
令和5年度 実証授業「5年マット運動」@世田谷区立給田小学校 R5.10.23これまでの研究